 第15回 議員の学校 第15回 議員の学校
|
|
「第15回 議員の学校」

11月16~17日、東京・多摩住民自治研究所主催の地方議員研修に行ってきました。
今回のテーマは「地域エネルギー政策の展望を学びあう~~福島・チェルノブイリ・ドイツ・日本~~」です。
申込み案内にある”福島原発事故から学ぶ最大の教訓は、一刻も速く原子炉を閉鎖して廃炉に導くこと、再生可能なエネルギーのプログラムを全国各地に実体化することです。元首相の「原発廃止」の発言が話題になっていますが当然のことです。
今回の企画は、福島の現地の大学を拠点に、チェルノブイリの事故から学び研究する努力を重ね、地方財政の角度からの自治体研究を進めてきた研究者によるじっくり講義と参加者の討論、そしてドイツ視察からの報告を交えて、日本における地域エネルギー政策の展望を学びあいます。”という呼びかけに意を決して、夜行バスに乗りました。
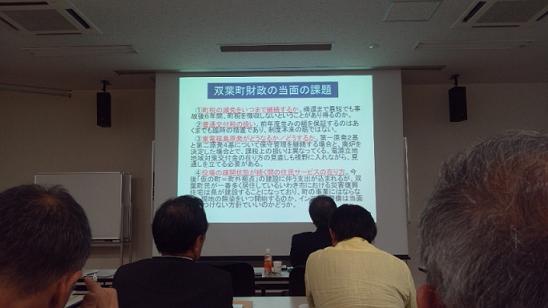
まず、福島大学清水教授の講義「原発から自然エネルギーへの政策転換と地域の自立」は今や地方自治体の問題として避けて通れない課題であり、日本は自然の持つ力が多様なので一律な施策はムリ…電力の固定価格買い取り制度が成立したため、向こう20年は儲かる!とみて大手企業の土地売買が始まっている⇒住民参加にしなければならない。
10日間燃え続けてプルトニウムやストロンチウムまで飛散したチェルノブイリの事故と福島の事故が同じ規模だったら、首都圏を含む近畿地方まで被害は及んでいた⇒避難不可能の最悪事態になっただろう。
*大震災・原発事故から3年近く経た今、復興のために何が必要か?
①被害者同士が対立している状況の克服(放射線の健康影響に関する共通認識の構築…県民健康管理調査は成功させなければならない)
②放射能汚染地域対策法(仮称)の策定(帰還基準の設定…1msvにこだわると戻れない現実がある。移住の選択と保護区の設定)
③避難者の生活再建の道筋提示(賠償・補償問題の処理・自立できる条件の整備)。
このような提起があり、次にドイツ・デンマークの調査から自然エネルギーへの転換を図っていくための講義がありました。
福島県は戦前から首都圏に電気を送ってきた経緯があり、猪苗代や只見川電源開発を経て、産業が乏しく都会への出稼ぎで暮らす浜通りへの原子力にシフトされてきたとのことです。福島県は、この教訓から「再生可能エネルギーへの転換」方針を出しました。
ここで日本の最大の問題は「発送電が電力9社の独占」ということです。
ドイツでは1998年にEU指令に基づき、発送電を分離して発電と小売りを自由化しました。日本のマスコミは「自然エネルギーが普及すればするほど、電気料金が上がる」と報道していますが、これは独占電力会社が君臨していることの克服と「再エネ賦課金の料金引き上げ効果は3割に留まる」という家の光協会が発行した文書に反論があります。
池上講師は「地方議員の責務」を随所にちりばめて話されました。
客観的な資料である千葉大学の「被災地を除く自治体の再生可能エネルギー導入促進のために独自に実施している政策」について1696市区町村に調査をしたところ、回答自治体は804(47.4%)!大震災・原発事故の半年後にもかかわらず、全国の自治体のなんと危機意識のないことか!(我が横手市は試験導入段階?)→自治体自らが計画を立てないと、大企業に乱開発される怒れが大きい。技術を持っている大企業の参入自体は良いが、いきなり大規模に造らせないこと!将来に向かって公共的なプランを作れるのは地方自治体であり都市計画として行政に乗せていくと発展しない。しっかりとした条例が必要。
結論として、地方議会に身を置く私たちのするべきことは
①再生可能エネルギーについての学び合いをひろげる(住民全体の認識も広げる理論的学習と先進地のみならず自分たちの地域をよく見て回る現場学習。そしてどんな制度があるのか。何をして良いのか。何をしたらいけないのかの政策学習)
②市民運動をつくり発展させる(主体的な活動姿勢を貫く。事業主体を作り協同出資・協同分配をする)
③自治体政策の転換・発展(地域内循環型のエネルギー政策を進め、最も効率の悪い電気は後でよい。一次エネルギーのまま地中熱や水利、木質バイオマスなどの熱利用・動力利用に取り組むべき。そのもとで、地域産業と雇用計画を立てる。国や県市の責任分担と市町村優先の原則を貫く)。
最後に「議員は自分より若い世代のことを常に考えるべき」ということと、日本における再生可能エネルギーの中心は、国土の65%を占める森林と、生ごみなどの発酵熱を重視するバイオマスになるだろうと示唆してくれました。
「地方議会では、どういう考えかたで施策を進めるべきなのか、多数決ではなく全会一致を勝ち取ることが必要であり、市民的モラルが形成されていくことを目指そう」というお話を肝に銘じて帰りました。
|
![]()