![]()
| ☆ | ☆ | |||
「第44回市町村議会議員研修会in岡山…2日目」 5月15日は約5時間の講義でした。愛知大学地域政策学部の鈴木誠教授による「地域産業政策・地域経済振興策への向き合い方を考える〜中小企業・小規模企業の振興条例の意義と活かし方を中心に」というお話です。 論点は、企業誘致一辺倒の施策を見直し、若者の行動力とネットワーク、ベテランは職業経験と老齢年金を活かし、多世代が共生しビジネスや会社を地域から興し、災害に強く回復力ある地域づくりを後押しする「中小企業振興基本条例」「小規模企業振興基本条例」「地域産業振興条例」などを制定し、地域社会から産業を興し育てることに価値をおく「産業自治」宣言が始まっている今、その意義や方法、成果や教訓等を多面的にとらえようというものでした。 内需=円を使う私達日本人が国産品と輸入品を買う場合の合計需要。 外需=外貨を持つ外国人が日本製品を日本国内及び母国などで買うことによる需要。 ▲もうけを蓄えてきた大企業が利益を所得に還元してこなかったことの影響が大。 ➡地域振興策のポイント ①外貨に過度に依存したグローバル経済の動向に翻弄されないこと。 ②生産・分配・支出の経済活動が営まれる自治体単位に、ヒト・モノ・カネ・情報の地域内循環が必要。 ③見える化=条例を通じて、基本理念、基本的施策、推進体制を明文化することが重要。 ④それらを踏まえて経済活動の繰り広げられる地域社会の安定を促進する。 ➡農・工・商のみならず、全国的に切迫している医療・介護の分野で地域経済を発展させていく取り組みを、広島や福山など医療生協の活動で紹介されました。 富士宮市などでは既に策定した振興条例の見直しにあたって商工会議所、商工会、民主商工会と行政とが一緒になった詳しい実態調査をしています。我が横手市は…どこまで具体策を講じてきているか、地域包括ケアひとつをとっても縦割り?…という思いが誤解であるように、しっかりと検証しなければ!と痛感しました。 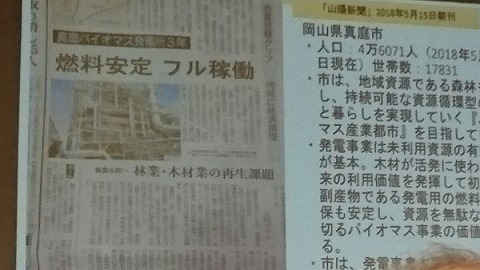 |
||||
| これまでの記事 |
||||