![]()
| ☆ | ☆ | |||
「第50回公的扶助研究全国セミナーin盛岡……報告その4」 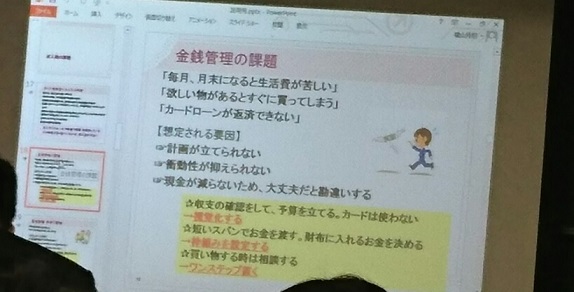 11月12日、広大な岩手大学での研修も最終日です。 特別講座「社会福祉現場の中で考える 大人の発達障がい~貧困と発達障がいとの関係について」。 50人ほどの参加者はほとんどが生活保護のケースワーカーや生活困窮者自立支援事業を担当している方々で、日々直面している深刻なケースの質問が相次ぎました。まずイントロダクションを紹介します。 「私たちが支援するかたの 中には、日常生活の様々な場面で多くの困難や生きづらさを抱えているかたがいます。 しかしそれらが”発達障がい”に起因するものであることを ご本人も周りの人も理解できず、さらに生きづらさを増長させてしまっている場合があります。 その中には、うまくコミュニケーションが取れずに 仕事が継続できない人や、そして人間関係に悩み、うつ病を発症してしまう人もかなりいます。 そういう意味では、貧困問題の中に発達障がいを 持つ人がかなりの数いると思われます。互いに障がいへの気づきがないために、誤解や不具合が生じています。 その”困っている”人たちへの 支援の在り方を共有したいと思います。」 *発達障がいは、親の育て方には関係なく、生まれつきの脳機能の障がいである。 *その状態は一人一人 違うものであり、理解するには、発達障がいの特性を知ることが大切…プラスとマイナスの部分を持つ。例えば「社会性」=協調性に乏しい面と ユニークな発想ができる面がある。「コミュニケーション」=抽象的な会話が理解困難の面と、裏表がなく独特の発想や表現ができる場合がある面 など。 *特性と環境の関係から、本人に合う対応や資源を探ることが必要。 *丁寧な機関連携が必要=発達障碍者支援法が成立し自治体に支援の機関が複数設置されつつあるが、相談機関ごとに重なり合う連携でなければならない(すき間をつくらない。本人をまじえたカンファランスが大切)。 *私たち議員もそうだが、相談を受けたら一人で請け負わないこと!周りにいる専門職に相談し、集団で支援していくことが本人にも家族にも必要。 この三日間のキーワードは「実のある連携」「当事者を中心に、より良い方法を見出していく」ということだと学びました。学校を出てから45年も経った今「イーハトーブの学び舎」で学生さんに混じっての勉強、そして生協食堂でボリュームたっぷりのランチを堪能した有意義な時間でした。 |
||||
| これまでの記事 地元学'のすすめ 学びのカフェ 講義Ⅰ 交流会議2017 |