 こども、子育て支援新制度と自治体行政の課題 こども、子育て支援新制度と自治体行政の課題
|
|
「こども、子育て支援新制度と自治体行政の課題」
7月28日仙台から東京に向かいました。地下鉄大江戸線に乗り、牛込神楽坂駅から地図を頼りに歩くこと12分。可愛い看板「保育プラザ」が見えてきました。

ウィンドウには保育者と父母を結ぶ雑誌「ちいさいなかま」の大きなポスター!。嬉しくなって汗だくのまま会議室に入った私…50人ほどが集まって密度の濃い半日を過ごしました。
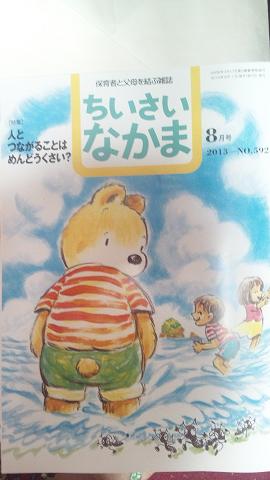
4月の議員研修〜5月の横手市行政と市民との勉強会〜7月の秋田県内関係者と内閣府の合宿研修…と学習を重ねてもなかなか展望が見えず、最終的な国の方向をキャッチして9月議会の条例を確かなものに制定できるよう、ぜひとも情報を得たい!との思いから参加しました。
まずこれまでの民主、自民、公明の三党合意による修正=こどもの保育、教育に格差をつけないことで児童福祉法24条1項が復活し、保育所は市町村が実施責任を持つことになりました。そして幼保連携型認定こども園への移行を強制しないことも確認されました。
しかし安倍政権は株式会社に門戸開放を念頭に置いていて、こどもと親の育ちは二の次だということが、何回も出される「よくある質問Q&A」に表れています。今日学んだポイントは
1、人口減少は進むとしてもニーズ調査では全国的に4割の親が3歳未満児の施設入所を希望しているし潜在していること。
2、地域型保育の場合は3歳になると、保育所か幼稚園か認定こども園のどれかに行くことになるが、連携できる施設をさがすことが迫られる。
3、認定こども園について。幼稚園と保育所の2施設の連携なので二人の園長がいた。しかし新制度では単一の施設になるため園長は一人になりその分人件費が減額される。保護者と園の直接契約になり、その場合入園希望があっても「正当な理由」があれば園側が受け入れを拒否できる…
障害児が拒否される懸念強い。保育時間が親の就労形態によるため様々になり、保育現場で混乱が起きやすい。教育と保育の差別が意識改革できない関係者達が非常に多い。
*そもそも保育所保育指針と幼稚園教育要領はきちんと擦り合わせて作られたもので、教育の5領域は確保できている!
などが確認できました。
横手市議会でも9月議会に条例が作られます。これからのこども達や保護者、保育者などみんなが納得でき、拠り所になりうる条例をつくるため、職員さん、市民みんなでよりよい条例をつくるには、ディベートではなくファシリテーションで取り組まなければと通感しました。 |
![]()