 抧堟堛椕栤戣傪峫偊傞 抧堟堛椕栤戣傪峫偊傞
|
|
丂
丂乽抧堟堛椕栤戣傪峫偊傞乿
丂8寧11乣12擔丄愬戜傑偱崅懍僶僗偱2帪娫敿丄愬戜墂偲側傝偺TKP愬戜僇儞僼傽儗儞僗僙儞僞乕偱偺抧曽媍堳尋媶夛偵嶲壛偟傑偟偨丅
乭抧堟堛椕嵞惗傊偺張曽獬乭偲偄偆僄僗僾儕偺岠偄偨丠僥乕儅偱丄丒側偤堛巘晄懌偑婲偒傞偺偐丅丒偙傟偐傜抧堟堛椕偵婲偒傞偙偲乣幮夛曐忈偲惻偺堦懱夵妚偺堄媊偲抧堟傊偺塭嬁丅丒帺帯懱媍堳偺壥偨偡傋偒栶妱偲偄偆撪梕偱偟偨丅
丂巹偲偟偰偼乽揤壓偺埆朄乿偲偟偐懆偊傜傟側偄乭幮夛曐忈偲惻偺堦懱夵妚乭偵偮偄偰乽堄媊乿偭丠偲栚偔偠傜傪棫偰偨偔側傞崁栚偩偭偨偺偱乽悽偺偍偍偐偨偺恖乆偼偳偆峫偊偰偄傞偺偐乿傪曌嫮偡傞昁梫偑偁傞偲巚偭偰偺尋廋嶲壛偱偡丅
丂島巘偺埳娭桭怢忛惣戝妛宱塩妛晹嫵庼偼丄導怑堳偺宱尡傪偍帩偪偱丄帺帯懱昦堾偺宱塩曄妚丒抧堟堛椕栤戣側偳偺峴惌妛偑偛愱栧偱偁傝丄慡崙偺抧曽偵偁傞條乆側堛椕婡娭傪栤戣揰傗摿挜傑偱幚偵徻偟偔偛懚偠偺曽偱偟偨丅巹偑堦斣偆傟偟偐偭偨偺偼丄帒椏偑僷儚乕億僀儞僩偲傎傏摨偠偱丄偲偰傕戝偒側暥帤偩偲偄偆偙偲偱偡両丅
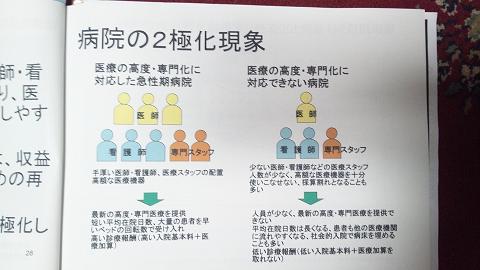
丂弶擔偼乽抧堟堛椕嵞惗乿偵偮偄偰偱偟偨丅
嘆慡崙偱怺崗側堛巘晄懌乮導挕強嵼抧埲奜偱丄愄偼嫆揰昦堾偩偭偨強偑摿偵怺崗亖墶庤巗偱傕乯
乧尨場乮1乯1982乮徍榓57乯擭偐傜堛妛晹掕堳偺嶍尭傪妕媍寛掕乮戞擇椪挷偵屇墳偟偰乯仺堛椕曵夡偑恑傒2008乮暯惉21乯擭偵堛妛晹掕堳憹傪妕媍寛掕偟偐偟惉壥偼10擭屻丅
乮2乯堛椕偺崅搙丒愱栧壔丗偙傟帺懱偼椙偄偙偲偩偑丄20擭慜偼1恖偺堛巘偑姵幰偺昦婥傪恌偰偄偨仺尰嵼偼暋悢偺愱栧壢偺堛巘偑1恖偺姵幰偺幘昦傪恌傞乮怱憻幘姵傪暪敪偟偨摐擜昦姵幰偵懳偟丄愄偼撪壢堛侾恖仺崱偼摐擜昦愱栧堛亄怱憻昦愱栧堛亄曻幩慄愱栧堛乯
乮3乯恖岥偺媫寖側崅楊壔丗挿婜娫堛椕傪庴偗傞枬惈幘姵偑懡偄丒昦堾巰偺憹壛亖堛椕幰偺晧扴憹丅
乮4乯僀儞僼僅乕儉僪僐儞僙儞僩丗戝愗側偙偲偩偑丄姵幰傊偺廩暘側愢柧偲摨堄偺昁梫惈偼堛巘偺巇帠傪憹傗偡丅
乮5乯彈惈堛巘偺憹壛丗抝彈嫟摨嶲夋偺棫応偐傜偼摉慠偩偑丄椪彴尰応偐傜棧傟側偔偰傕偡傓傛偆側幮夛峔憿乮抝彈偲傕偵儚乕僋儔僀僼僶儔儞僗偺曐忈乯偑昁恵丅
乮6乯楎埆側楯摥娐嫬丗夁楯巰悺慜偱18%偺堛巘偑惛恄揑偵捛偄崬傑傟偰偄傞丅
乮7乯怴椪彴尋廋惂搙乮2004擭乯丗怴恖堛巘偑尋廋傪庴偗偨偄昦堾傪慖傃丄昦堾懁偺婓朷偲偮偒崌傢偣傞惂搙偑怴偨偵摫擖仺懡偔偑搒夛偺戝昦堾傪尋廋愭偵慖傇寢壥偵仺堛椕岠壥偑柧妋側媫惈婜傪巜岦偡傞堛巘偼丄崅搙丒愱栧壔偵懳墳偟丄堛巘悢偺懡偄昦堾偵廤傑傞仺怴偟偄抦幆傗媄弍傪恎偵拝偗丄廻捈摍偵梋桾偁傝仺昦堾偺擇嬌壔両偟偐偟尋廋2擭栚偵堦偐寧娫丄抧堟堛椕幚廗偺尋廋偑偁傞偺偱丄帺帯懱偑偙偺揰傪傕偭偲埵抲偯偗傞傋偒偱偁傞丅
乮8乯崙柉偺堛椕傊偺晄棟夝乮寬峃偵偮偄偰晄曌嫮側姵幰丒崙柉丒僐儞價僯堛椕巜岦乯丗僞僋僔乕戙傢傝偺媬媫幵巊梡丒帺桼婥傑傑偵媥擔傗栭娫恌嶡傪庴偗傞摍乆丅
嘇帺帯懱昦堾丒恌椕強偺懚嵼堄媊
乮1乯2009擭10寧偺慡崙偺堛椕巤愝悢忬嫷偼8733昦堾拞丄帺帯懱昦堾偼11.5%丅偟偐偟婎姴嵭奞堛椕僙儞僞乕傗傊偒抧堛椕嫆揰昦堾丄戞1庬姶愼徢巜掕堛椕婡娭偼50%埲忋偑帺帯懱昦堾偑扴偭偰偄傞丅
乮2乯堛椕曵夡偺夝寛嶔偲偟偰2008擭偐傜堦斒夛寁孞傝擖傟偑1000壄墌憹妟仺巜掕娗棟偐柉娫傊偺曽岦丗帺帯懱昦堾偼昁梫側偺偐丠
乮3乯昦堾偺採嫙偡傞堛椕僒乕價僗偺惈奿偑曄傢偭偰偒偰偄傞丗徍榓帪戙偼栻傗拲幩側偳偵恌椕曬廣偑廳揰揑偵攝暘偝傟偨仺偱偒傞偩偗恖傪尭傜偟偰棙塿傪摼傞丅尰嵼偼恌椕曬廣偼媄弍偵懳偟偰揔愗偵攝暘偝傟傞偙偲傪栚巜偟偰偄傞仺僒乕價僗傪採嫙偟偰廂塿傪忋偘傞嬈懺偵偡傞仺恖傪屬傢側偗傟偽棙塿偑摼傜傟側偄丅
嘊堛巘偑嬑柋偟偨偔側傞傛偆側抧堟偵偡傞偵偼
乮1乯峴偆堛椕傪柧妋偵偡傞乮偁傟傕偙傟傕媮傔側偄乯
乮2乯夁崜夁偓側偄嬑柋偲揔愗側曬廣傪曐忈偡傞
乮3乯堛椕媄弍傪妛傋傞丄帺屓偑惉挿偱偒傞丄愱栧堛偺帒奿偑庢傟傞巤愝偵偡傞
乮4乯廧柉偑姶幱偟丄揔愗側庴恌峴摦傪偡傞乧尰応偱摥偔堄巚偺榖傪椙偔挳偐側偗傟偽堛椕婡擻偺嵞曇偼偆傑偔偄偐側偄丅廧柉傗峴惌偑彑庤偵悇恑傗斀懳偺媍榑傪偡傞偙偲偼NG.
仏抧堟偺昦堾偱乽憤崌恌椕堛乿傪堢偰傞乧抧堟廧柉偺惗妶廗姷傪娷傔偨恎懱偺慡偰傪恌傞擻椡丒廧柉偺寬峃偵娭偟偰廧柉傗峴惌偵摥偒偐偗丄楢実偟偰偄偔椡丄幮夛揑側僐儈儏僯働乕僔儑儞擻椡摍乆偼丄抧堟偺昦堾偱嬑柋偡傞偙偲偱恎偵拝偗傞偙偲偑偱偒傞丅
嘋廧柉傕抧堟堛椕偺摉帠幰丗廧柉偺晄埨偼丄惌帯丒峴惌丒僐儈儏僯僥傿偑夝寛偡傋偒傕偺偱偁傞丅
乮1乯晄埨丒柍娭怱丒懠恖擟偣傪側偔偟偰偄偔偨傔偵偼廧柉帺恎偑帺暘偺懱傗昦婥偵偮偄偰姶怱傪帩偮丅堛椕傗寬峃偵偮偄偰妛傇拠娫傪帩偮丅
乮2乯抧堟堛椕偺嵞惗偼柉庡庡媊偺嵞惗偵宷偑傞乧帺暘偨偪偺寬峃偵娭偡傞偙偲偩偐傜丄偒偪傫偲偟偨忣曬採嫙偲廧柉偺娫偺媍榑偑偁傟偽丄恖乆偼愡搙偁傞峴摦傪偡傞壜擻惈偑偁傞仺抧堟偺柉庡庡媊偺嵞惗乣乣偲偄偆棳傟偱妛傃傑偟偨丅
丂媫惈婜丒垷媫惈婜偺憤崌昦堾傪俁偮桳偡傞変偑墶庤巗丅偡傒傢偗傪柧妋偵偟丄挿栰導傪儌僨儖偲偡傞抧堟堛椕丒寬峃悇恑傪揙掙揑偵幚慔偡傞偙偲偼壜擻偺偼偢偱偡丅峴惌傕媍夛傕廧柉傒傫側偱杮崢傪擖傟偰庢傝慻傓帪偩偲巚偄傑偟偨丅 |
![]()