 乽抧堟堛椕栤戣傪峫偊傞乿尋廋曬崘丂噦俀 乽抧堟堛椕栤戣傪峫偊傞乿尋廋曬崘丂噦俀
|
|
丂
丂乽抧堟堛椕栤戣傪峫偊傞乿尋廋曬崘丂噦俀
擇擔栚偺尋廋壽戣偼乽偙傟偐傜偺幮夛偲幮夛曐忈乿偵偮偄偰偱偡丅
嘆偙傟偐傜偺抧堟偲峴惌偼丄偳偆側偭偰偄偔偺偐丠乣乣崱丄抧堟偵婲偒偰偄偰偙傟偐傜堦憌恑傓偙偲
乮1乯崙嵺壔丒忣曬壔偺恑揥偲幮夛偺擇嬌壔乧IT偺恑曕偼恖椶偺惗妶偵朙偐偝傪梌偊偨丅摨帪偵晧偺懁柺
亖TPP偵傾儊儕僇偑壛擖仺婯惂娚榓偺壙抣婎弨偑悽奅偺婎弨偵丅
丂乽堛乿仺旕娭惻忈暻偲偟偰尨懃擣傔傜傟偰偄側偄乽崿崌恌椕乿傗姅幃夛幮偺堛椕嶲擖夝嬛偺壜擻惈仺崙柉奆曐尟惂搙偺曵夡偵丅
仏柍惂尷偵崿崌恌椕傪擣傔傞偲昻晉偵傛傞奿嵎丒堛巘偺抧堟曃嵼偺壜擻惈戝偵丅
帯椕岠壥偺側偄嵓媆揑堛椕偑憹偡壜擻惈戝丅
仏傾儊儕僇偺堛椕丗塮夋乽僔僢僐乿偵擛幚亖柍曐尟幰偑恖岥偺15%丅
嘇妋幚偵婲偒傞偙偲亖媫寖側崅楊壔乮摿偵搒巗晹偺搒摴晎導乯偵敽偭偰婲偒傞偙偲
丂
乮1乯堛椕丒夘岇偺愨懳揑側帒尮晄懌
乮2乯堛椕丒暉巸丒擭嬥偺巟弌偺憹戝
乮3乯惻廂偺尭彮乧摿偵屌掕帒嶻惻偺尭彮孹岦偑戝偒偄
乮4乯偦偺堦曽乧抧堟偵偼尦婥側崅楊幰偑懚嵼偡傞
嘊抧堟偵偍偗傞屄恖偺屒棫偺奼戝乮偝傜偵怺崗壔偑梊憐偝傟傞乯
乮1乯斶嶴側帠審偺憹戝乧帣摱媠懸憡択懳墳審悢偑10擭娫偵4攞壔丒憇擭憌偺屒撈巰丅
乮2乯幮夛晄埨憹戝丂仺峴惌晄怣憹戝
乮3乯抧堟廧柉偺憡屳晄怣
乮4乯幮夛揑僐僗僩丒峴惌僐僗僩偺憹戝仺僑儈壆晘丗抧堟偺屒棫傪尭傜偝側偗傟偽傕偭偲憹偊傞丅
嘋崙丒抧曽帺帯懱偺婡擻楎壔乧愴屻丄擔杮偺岞柋堳慻怐偼攑毿偺帪戙偐傜棫偪忋偑傝晄懌偡傞廧戭丒岎捠丒嶻嬈丒嫵堢丒曐寬丒堛椕側偳偺恖揑丒暔揑側婎斦惍旛偵恠椡偑丄朙偐偵側偭偨備偊丠偺栤戣乮帣摱媠懸丒傂偒偙傕傝丒儂乕儉儗僗乯偼拞墰廤尃偱偼夝寛偟側偄丅
仏幮夛栤戣夝寛偵偼乽恖乿偑昁梫丅乧摿偵寖憹偡傞崅楊幰傪偄偐偵巟偊傞偐両
巗挰懞乮尰応偵嵟傕恎嬤乯偑娭學幰偲抦宐傪峣偭偰廧柉偲偲傕偵摦偔傋偒丅
嘍愨懳揑側堛椕帒尮晄懌偺壓偱崙偺幮夛曐忈惌嶔偼偳偺傛偆偵摦偔偐両
乮1乯幮夛曐忈偲惻偺堦懱夵妚乧惌帯傛傝傕姱椈庡摫偺峫偊
仺丂昁梫側僒乕價僗偼偒偪傫偲丒嵿尮偼偲傝堈偄徚旓惻両両
仺丂宨婥偑棊偪崬傓寽擮戝偒偄丅
乮2乯尰忬乧擭嬥丗堛椕丗暉巸乮夘岇傗巕偳傕乯亖俆丗俁丗俀偺梊嶼妱崌
偙傟傪丄幮夛曐忈偺埨掕壔偵4%暘丒幮夛曐忈偺廩幚偵1%暘巕偳傕乮0.7挍墌乯丒堛椕夘岇乮1.5挍墌乯擭嬥乮0.6挍墌乯
丂丂
乮3乯徚旓惻偑10%偵側傟偽憡墳暘梊嶼傪憹傗偡亖偁偔傑偱傕姱椈懁偺峫偊偟偐偟島巘偼柧妋偵尵傢側偄偑丄偙傟傑偱偺徚旓惻偼暉巸偵偼巊傢傟偢両
乮4乯堛椕丒夘岇僒乕價僗採嫙懱惂夵妚傪傒傞偲乣堦掕偺埨掕懱惂丂丒擖堾堛椕偺婡擻暘壔丒嫮壔偲楢実乧媫惈婜丒垷媫惈婜丒枬惈婜丒抧堟曪妵働傾懱惂偺惍旛乧嵼戭堛椕偲嵼戭夘岇偺廩幚
仏導偑價僕儑儞傪偮偔傝栶妱偼奼戝偡傞偑惌嶔愑擟偼偁偄傑偄
仺丂巗挰懞傕堛椕價僕儑儞傪偮偔傞傋偒亖堛椕丒夘岇丒徚杊丒杊嵭摍乆
丒崅楊幰傕夘岇幰摍娭學幰傕嵼戭偱書偊崬傑側偄傛偆偵偡傞偙偲両
丒偐偐傝偮偗堛亖奐嬈堛堦恖偱偼尷奅仺丂儅僢僾偱暘愅偑昁梫
嘐堛椕夘岇憤崌悇恑朄丗2025擭乮戞1師儀價乕僽乕儉悽戙偑75嵨埲忋偵側傞乯傪尒悩偊偰丄帩懕壜擻側僒乕價僗採嫙懱惂偺妋棫傪傔偞偡偲偟偰崱擭6寧惉棫
乮1乯夘岇曐尟棙梡椏傪崅妟強摼幰偼1妱仺2妱偵憹妟乮婎弨偑濨枂偺傑傑乯梫巟墖傪夘岇曐尟偐傜彍奜丒摿梴儂乕儉擖強傪梫夘岇俁埲忋偵側偳栤戣揰偑懡偄
乮2乯抧堟曪妵働傾僔僗僥儉峔抸傪庯巪偲偟偰偄傞偑丄朄棩忋丄嵟廔愑擟偼丂崙丠丂搒摴晎導丠丂巗挰懞丠丒丒丒丒丒寛傑偭偰偄側偄両
乮3乯偟偐偟拞妛峑嬫傪抧堟曪妵働傾偺僄儕傾偵偡傞偙偲偑寛傑偭偨埲忋巗挰懞偺栶妱偑戝偒偄丅
仏僉乕儚乕僪偼楢実亖娭學幰偑楢実偡傞偨傔偵僐儈儏僯働乕僔儑儞傪恾傞偙偲偑廳梫偲側傞亖娭學幰傪偄偐偵偮側偖偐両亖亖峴惌偺栶栚偵側傞
仏抧堟廧柉傪偍媞條偵偟偰僒乕價僗偡傞傗傝曽偼俶俧丏
抧堟廧柉乮巗惌楢棈堳丒柉惗埾堳丒幮夛暉巸嫤媍夛丒NPO摍乆偲堦弿偵側偭偰偑傫偽傞怑堳.媍堳傕乯偑昁梫亖亖傑偪偯偔傝偺堄媊偑戝偒偄丅
埲忋偺尋廋撪梕偱偟偨丅
丂偦偺拞偱乽崙柉寬峃曐尟偺曐尟幰栤戣乿偵傕怗傟傜傟傑偟偨丅
丂搒摴晎導偼斀懳偟偰偄傞傕偺偺丄曐尟幰傪巗挰懞偐傜乮峀堟楢崌偱偼側偔乯搒摴晎導偵偡傞偙偲傪崙偼嫮椡偵恑傔偰偄傞偲丅
丂乽偝傜側傞岞旓偺搳擖乿偲朄棩忋偱偼宖偘側偑傜搒摴晎導扨埵偺塣塩偵偟掕棪晧扴妱崌傪尭傜偡曽岦偵偁傝丄偦偆側傞偲搒摴晎導偼嵿惌晧扴傪尭傜偡偨傔偵堛椕旓偺岠棪壔乮梷惂乯偵庢傝慻傑偞傞傪摼側偔側傞
仺丂寬峃悇恑偩偗偱偼側偄惌嶔偑導柉偵儅僀僫僗嶌梡丠両
寢榑丗崱屻丄抧堟偼杮奿揑側崅楊幮夛偵傛傞懚懕偺婋婡偵捈柺偡傞偙偲偵側傞丅
丂丂崅楊幰偑埨怱偱偒丄抧堟廧柉偑楢実偟偰娕庢傝偺偱偒傞幮夛偵偱偒傞乽傑偪偯偔傝乿傪寢壥揑偵側偟摼傞妶摦偑巹偨偪偺栶栚偲偄偆偙偲偱偟偨丅丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂
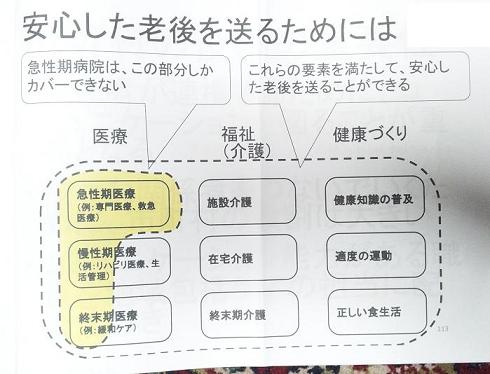
|
![]()