 城南高校 城南高校
銀杏同窓会総会
|
|
「城南高校 銀杏同窓会総会」
5月26日、母校の同窓会総会がありました。「横手高女」を卒業された大先輩から今年3月に卒業し、それぞれの道に進んで頑張っているニューフェイスまで200人が集いました。
いつもながらウルウルして歌えなくなってしまう校歌…幸田露伴の作詞による特に4番のサビのところ「♪ 銀杏の樹蔭 睦み合ひ 月日を経なむ たのもしく 銀杏の葉形 末広く 我が世を経なむ 幸多く♪」が好きです。
毎年、校長先生による講話が20分ほどあるのですが、今年4月に赴任された佐藤幸子校長のお話は、とても心に響きました。国語がご専門の先生による「新元号 令和 に寄せて~万葉集と時代背景~」というお題です。
①「令和」の由来は万葉集五巻「梅花の歌」の序文から出ている(天平二年正月十三日=今の2月…太宰府にて。奈良時代に中国から伝来し梅の実をいぶして薬として使った。梅は当時は特権階級の花。
②万葉集とは本居宣長によれば「よろずの言の葉」という意味だがはっきりはしていない。7世紀前半の持統天皇が歌ったものから400年の長きにわたるものもある(全20巻・4500首以上)
③分類すると「三大部立…相聞(親子・兄弟・家族も)・挽歌(人の死を悼む・悲しみ)・雑歌(それ以外の歌)
④表記…万葉仮名(現代の子どもの名前に通じるものもある~沙也加など)
⑤時代背景…政治の変化を見る必要がある=大化の改新以後、大和朝廷の主権を確立させる時代:有力な豪族の長屋王が謀反の疑いをかけられ一族が自刃した「長屋王の変」以後、藤原氏による中央集権国家へ移行する頃だった。太宰府は国のカナメであり、白村江の戦いに敗れて百済の人々が日本に逃げてきた。朝鮮半島から大和朝廷を守るため防人が組織されて全国から身分の低い若者が福岡方面に駆り出された……
「防人の歌」を詠んでみよう!”父母が頭かき撫で幸くあれて 言ひし言葉ぜ(けとばぜ)忘れかねつる……幸くあれて←幸くあれと・けとばぜ←ことばぞ……おそらく東北地方の方言をそのまま歌ったのだろう。このように「古事記」や「日本書紀」は遣隋使や遣唐使が持ち帰った漢字を使って国威発揚の意図があったが、万葉集では言霊を大事にして口述に漢字を当てはめたと思われる→万葉仮名。
*この時代は寛容性があった(新しいものを恐れない)。百済の人々を受け入れ、文化や技術も入って来た=排除したり、そのまま使ったりせず、融合させて自分たちのものにしていった。
*「令和」の時代と「万葉」の時代は似ている。外国人受け入れの問題で、今の時代の私たちはどう捉えて生きてくか?融合して前へ進むことができるか?社会に巣立つ高校生たちと一緒に私たち大人はどう考え、行動すべきか?国の為政者に任せきりでいいのか?と難しい課題を投げかけられた講話だったと思います。
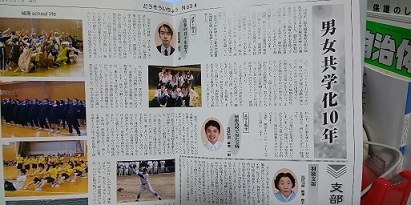 |
![]()
![]()