 避難所体験会~ 避難所体験会~
もしもの時の第一歩
|
|
「避難所体験会~もしもの時の第一歩」
3月20日、金沢孔城館で青年会議所主催の研修会がありました。商工会青年部やJA青年部に交じって、市役所危機管理課、市議会議員たちが集まり、日本赤十字秋田短期大学介護福祉学科の及川真一講師による、とても深い実践的な勉強をすることができました。
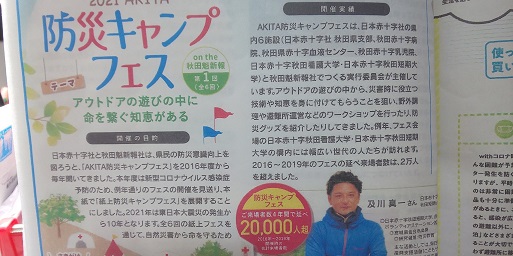
仙台市出身の講師は2011年の大震災を経験し、その年の4月1日から現在の職について以降も全国の災害復旧復興支援に尽力しながら「防災キャンプ」などのイベントを通して防災意識を高めるための普及活動を実践しておられます。
今日のテーマは①東日本大震災からの教訓②新たな防災の考え方③新型コロナウイルス④避難所設営体験…で、2016年から開催してきた「秋田防災キャンプフェス~アウトドアの遊びの中に命を繋ぐ知恵がある」のイベントを紹介しながら「ハッと」気づかされるお話を聴くことができました。まず
「災害予防」=日常の訓練。
「応急対策」=短期でできる。
「災害復興」=長期間の闘い…であり、この3つは住民とともにつくることが大事(住民とは小・中・高・大学生も必ず入る。アイディアは子ども・実現は大人)。
「自助」の意味を捉えなおすことも学びました。子ども・高齢者・障碍者みんながどうやって自分の身を自分で守るか!一人一人が強くならなければいけないと。
「公助」=行政は住民ではできないことをする役目があり、罹災証明書発行などの手続きを迅速に進めなければならない。だから「避難所」とは、行政の「場所貸し」であって、そこの「運営」は住民がやるべきこと。といったお話はとても考えさせられました。
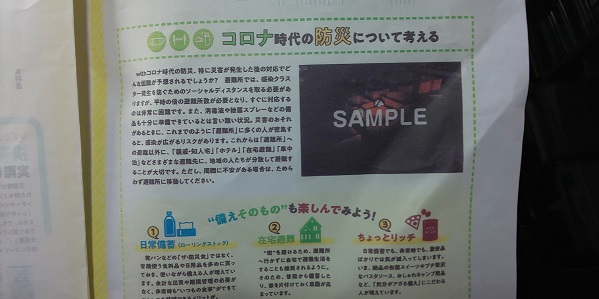
コロナウイルスについても、写真のようにたくさんの大切な資料を頂きましたが、大昔からコロナウイルスはいろいろあったけれども今回のCOVID‐19はこれまでのコロナウイルスと違い、経済を止めてしまうやっかいなものであり、手洗いと手指消毒についても相当しっかり洗わなければ効果がないことも実験されました。
最後は段ボールベッドや一人用のテント設営の実地体験です。横手市では組み立て式の段ボールベッドは一定保管していて新日本婦人の会でもセットの仕方を練習したりはしましたが、小学生でもセットできるビニールのテントが便利だし軽いし、さほど高額でもないし、折り畳み式の太陽光パネルなどもアウトドアショップで少しづつ揃えることも呼びかけていいのではないかと思いました。
今日のテーマである「もしもの時の第一歩」を私たちは何回かは避難訓練などを経験しているとはいっても講師の言われた「第一歩を踏んでいない人が多い」という多数派に属しているのではないかと思います。これから様々な機会をつくって、防災キャンプフェスを横手でも開催し、アウトドアクッキングや子ども連れの避難、避難所の感染症対策などを学ぶ必要があると痛感しました。
|
![]()
![]()