 第26回議員の学校 第26回議員の学校
第2講義
|
|
「第26回議員の学校 第2講義」
10月3日の2時間目は「相模原障害者殺傷事件にみる障害者差別の構造」というテーマで、元日本福祉大学教授の石川満先生による講義でした。
ここで私達が学ぶべきことは「貧困・差別の課題と地方自治~~今、自治体はなにをすべきか」です。
はじめに「このような事件は日本のどこでも起こり得る」と!措置入院問題だけに矮小化してはNG.障害者施策のあり方・福祉労働(特に障害者福祉)の実態・自治体や国のあり方を総合的に検討すべき。
*日本の障害者福祉は?
障害者自立支援法の意見訴訟において、国と和解し障害者基本法等が改正された。しかしその後は社会保障改革(改悪)により社会保障・障害者福祉は後退(国民の負担が増加し福祉内容は低下)→貧困・格差が拡大した…これについては私達は実感しているので、即同感!。それに伴い、国民の意識でも障害者差別や偏見が改善されなかった。
*「障害者の権利条約」=国際的な条約であり、自治体の条例に密接関連している→この権利条約を拠り所にして、自治体の施策を推進することが必要!=様々なところで公的責任を確立し、格差や差別をもたらさないような普遍的な社会保障制度を確立しなければならない…このミッションをもって石川先生の講義を受講しました。
先生は津久井やまゆり園の概要や歴史を説明されました。運営している社会福祉法人・かながわ共同会は第三者委員やオンブズマンを有し、優れた取り組みをしてきて神奈川県第一号の指定管理者制度による施設であると。
*犯人はなぜこのような思考(思想)を持つに至ったのか?
精神疾患だけで片付けられない。彼の思考は今日の日本の様々な問題が投影していることも見過ごしてはならない=「社会ダーウィン主義」(人間社会も自然に淘汰される)…しかし今はわからない。今後の留置鑑定で明らかになることを期待する。
*結論として
障害者の権利に関する国民の学びが決定的に不足=義務教育のカリキュラムの中で「障害者の権利」や「憲法(個人としての尊厳や居住権はく奪の重要問題提起)」国際的な権利についての学びを取り入れるべき…スウェーデンの中学校教科書に学ぶこと!
以上、大変深い内容の講義でした。
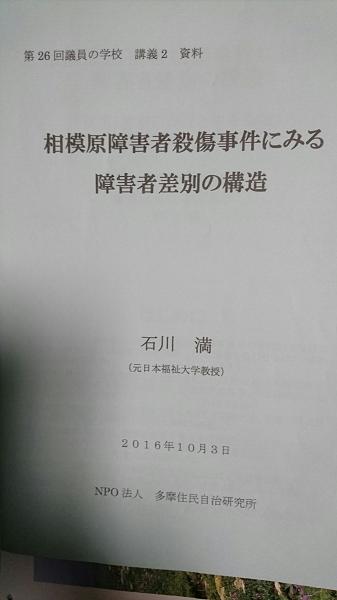
|
![]()